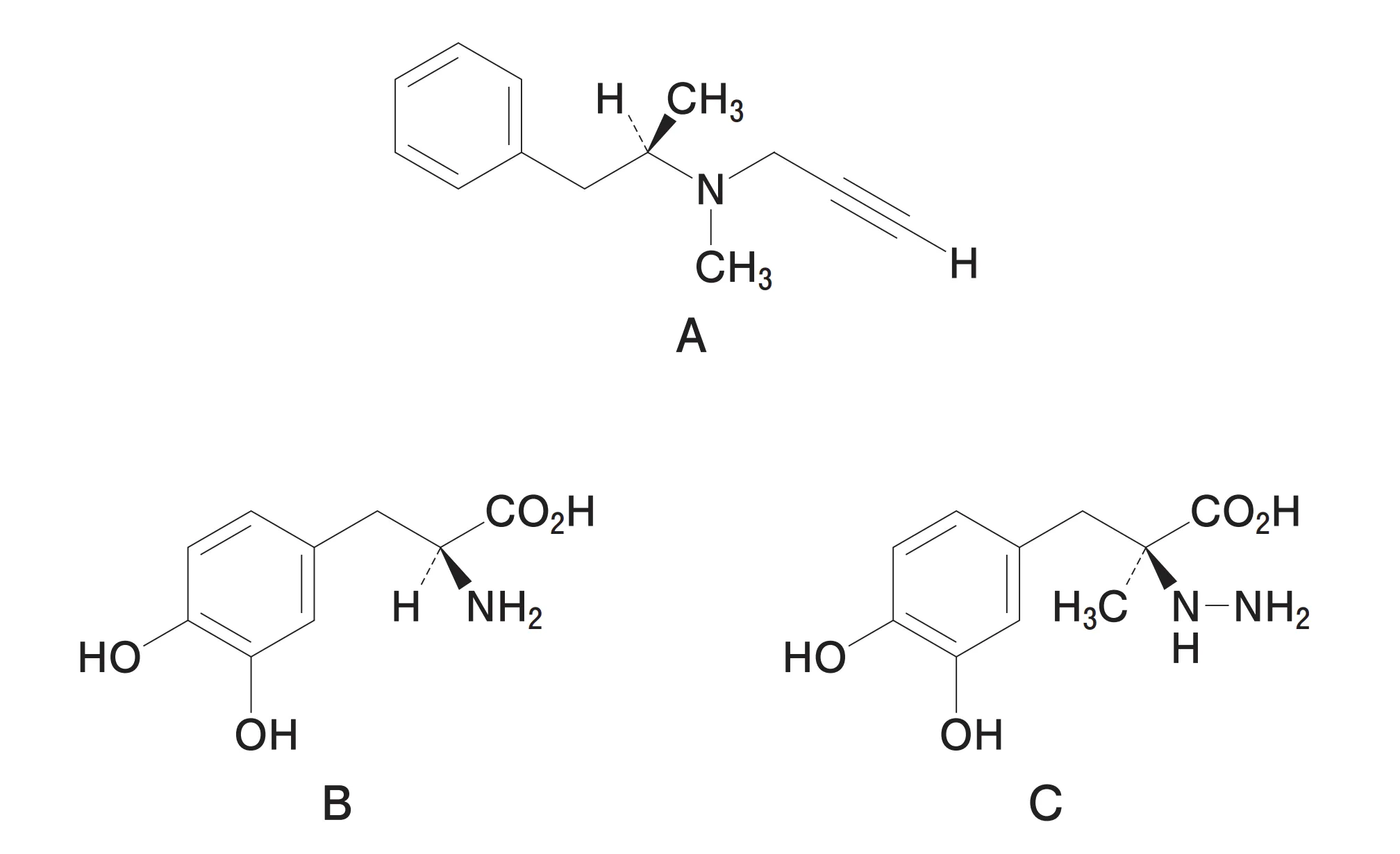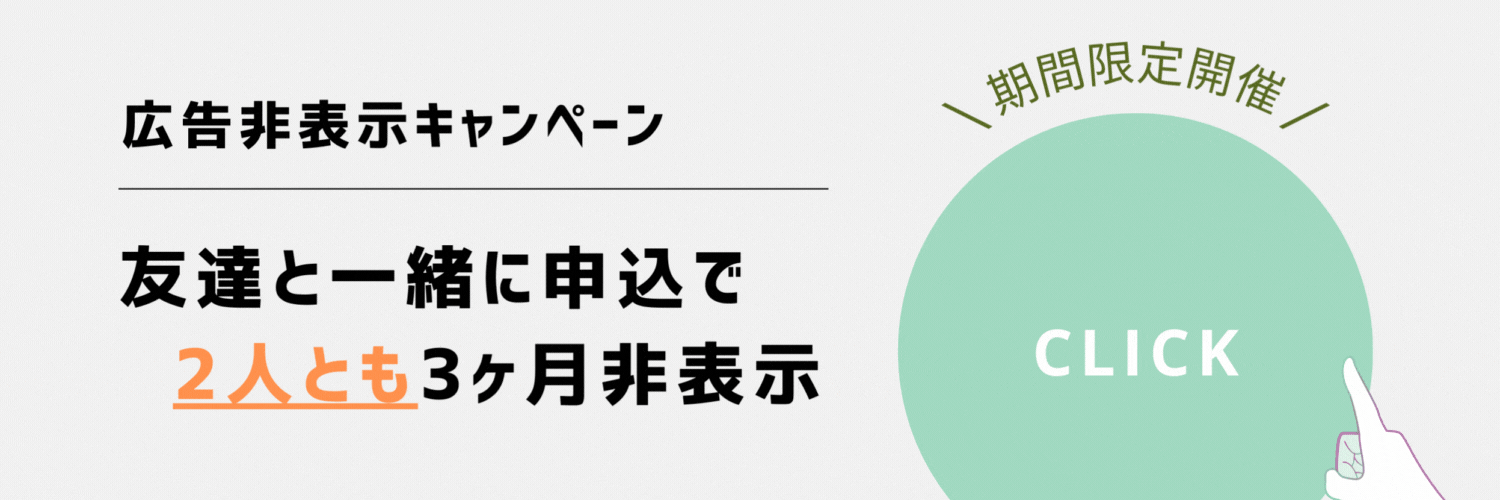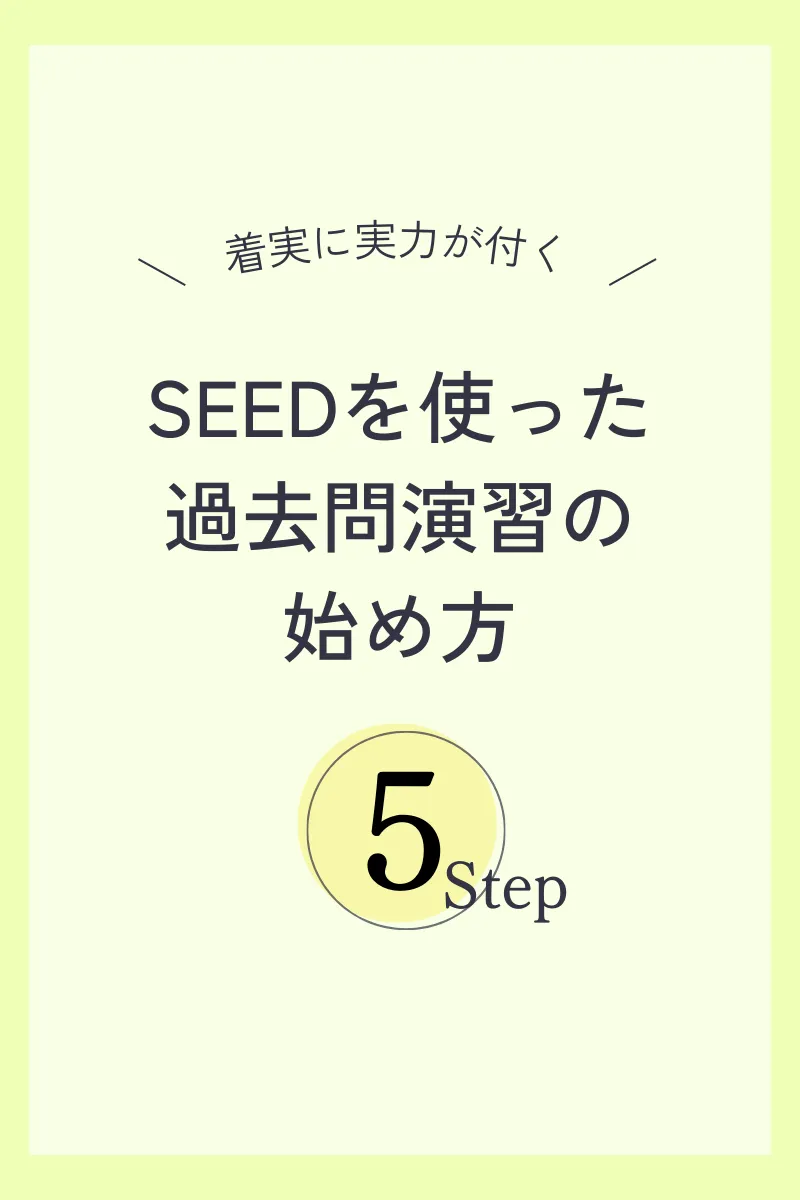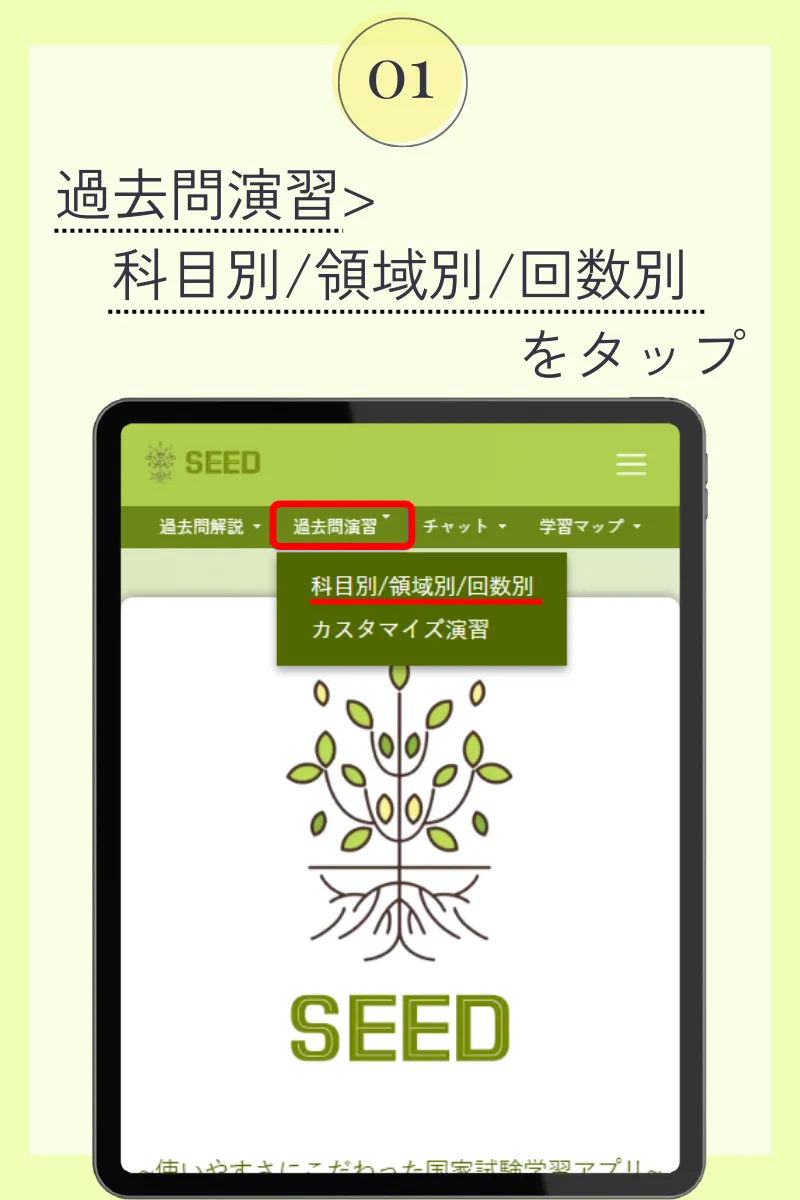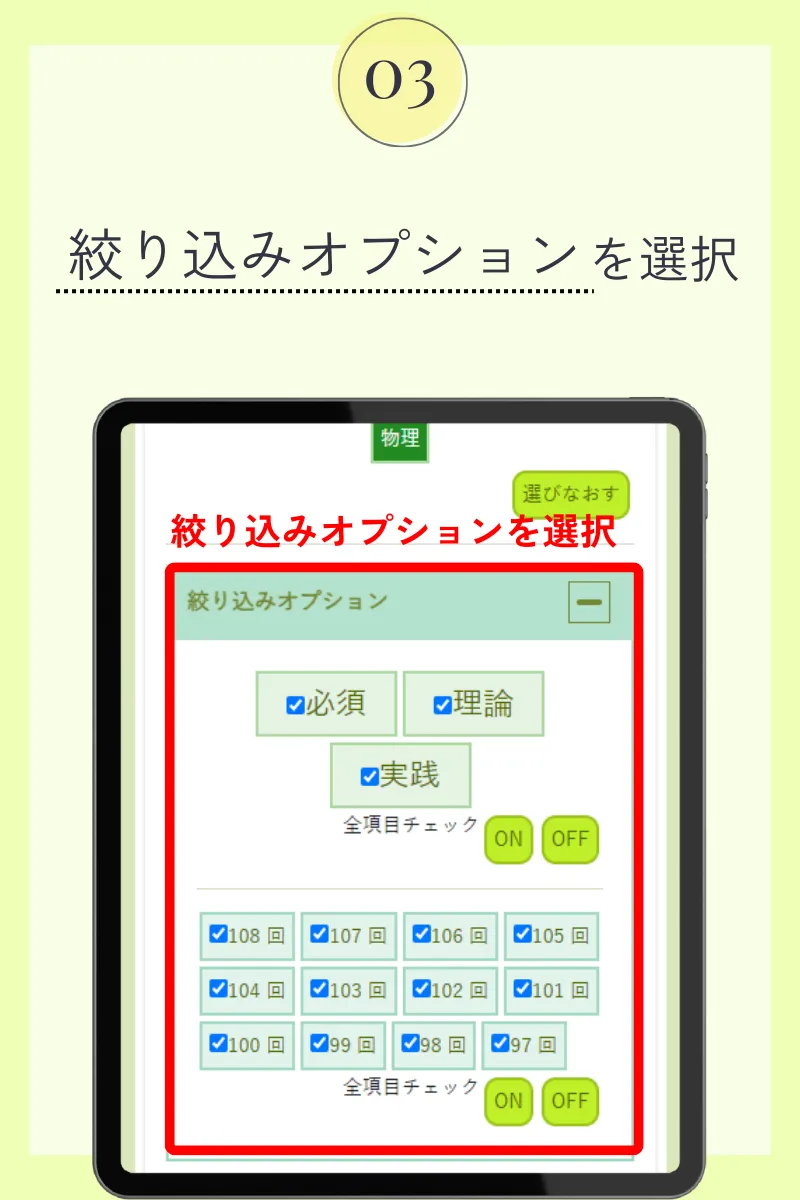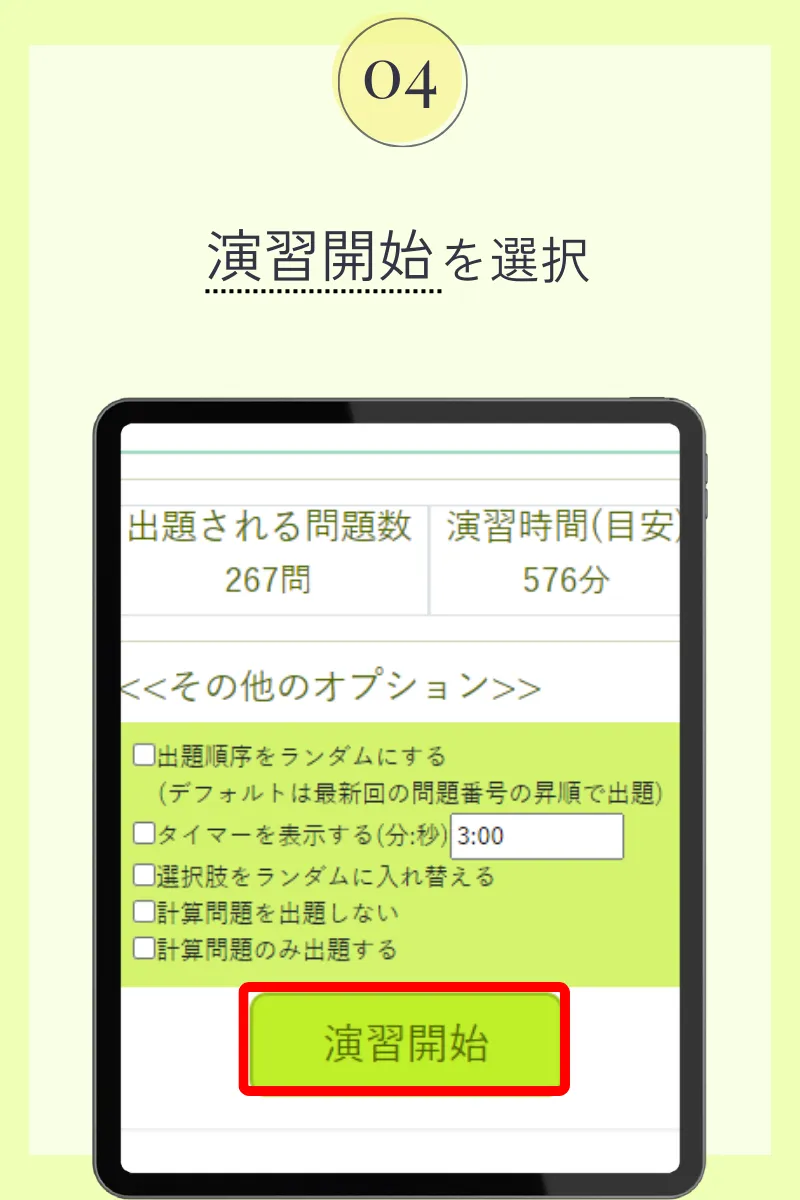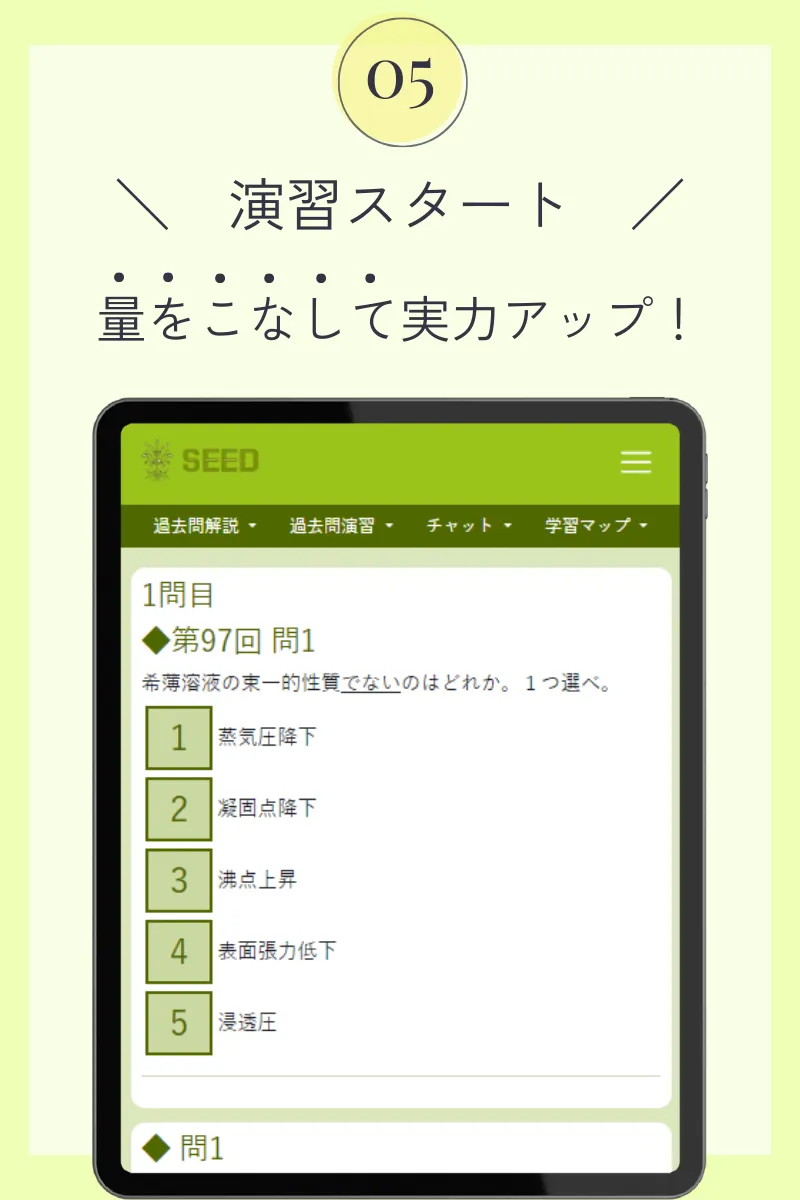第103回薬剤師国家試験
◆問208-209
78歳女性。高血圧症とパーキンソン病で処方1を服用していた。パーキンソン病症状のコントロールが困難になったため、新たに処方2が追加された。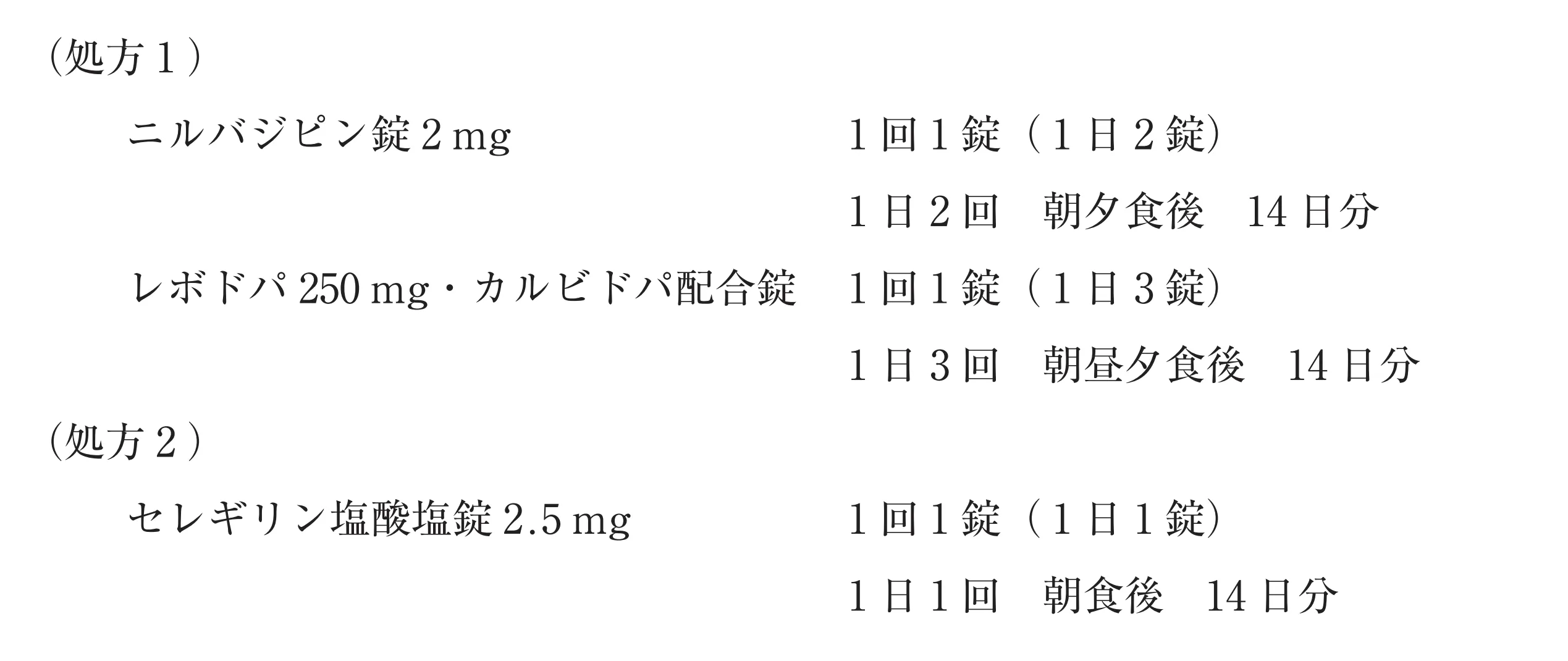
◆ 問208
本症例において処方2が追加された原因として、最も適切なのはどれか。1つ選べ。-
ウェアリング・オフ
-
ジスキネジア
-
悪性症候群
-
動悸
-
異常興奮
◆ 問209
◆ 問208
◆領域・タグ
◆正解・解説
正解:1
本患者はパーキンソン病を治療するため、レボドパ・カルビドパ配合錠を服用していたが、コントロールが困難なため、MAOB阻害薬であるセレギリン塩酸塩錠が追加投与されていることから、処方2が追加された原因として最も適切なのはウェアリング・オフであると考えられる。
<参考:ウェアリング・オフ現象が現れた場合の対処法>
・レボドパの服用量や服用回数を増やす。
・COMT阻害薬であるエンタカポンとレボドパを併用し、レボドパの効果を長続きさせる。
・MAOB阻害薬であるセレギリンなどを併用し、レボドパの効果を長続きさせる。
・レボドバ製剤にプラミペキソールなどのドパミンアゴニストを追加投与する。
◆ 問209
◆領域・タグ
◆正解・解説
正解:2、3
A〜Cの構造式について以下に示す。
A:セレギリン
セレギリンは血液脳関門を通過し、中枢内でMAOBを選択的に阻害する。それによりドパミンの分解が抑制され、ドパミンの作用が増強する。
B:レボドパ
レボドパはプロドラッグであり、アミントランスポーターにより血液脳関門を通過し、脳内で芳香族L−アミノ酸脱炭酸酵素による代謝を受けドパミンとなり作用する。
C:カルビドパ
カルビドパは末梢で芳香族L−アミノ酸脱炭酸酵素を阻害し、レボドパの分解を抑制する。それによりレボドパの脳内移行量が増大し、レボドパの作用が増強する。
1 誤
A(セレギリン)とC(カルビドパ)は、レボドパの分解を阻害するが、それぞれ異なる標的分子に働く。
セレギリンの標的分子:MAOB
カルビドパの標的分子:芳香族L−アミノ酸脱炭酸酵素
2 正
3 正
4 誤
Cは構造中に一置換ヒドラジン構造を有する。
5 誤:Cは、血液脳関門を通過しにくいことから、末梢で作用を示す。