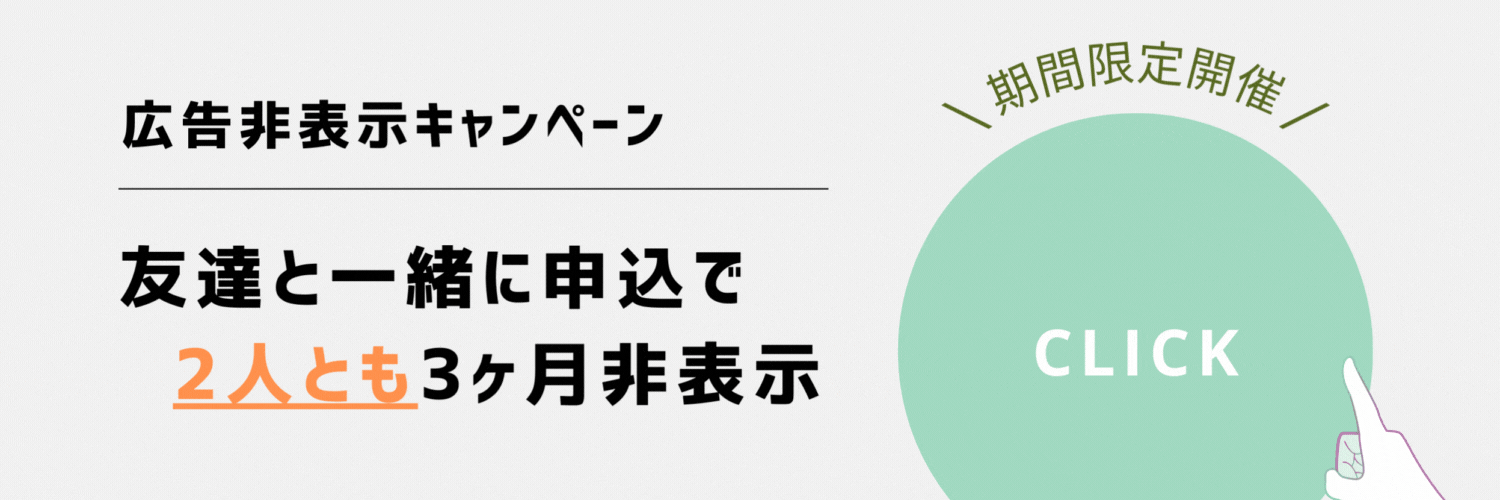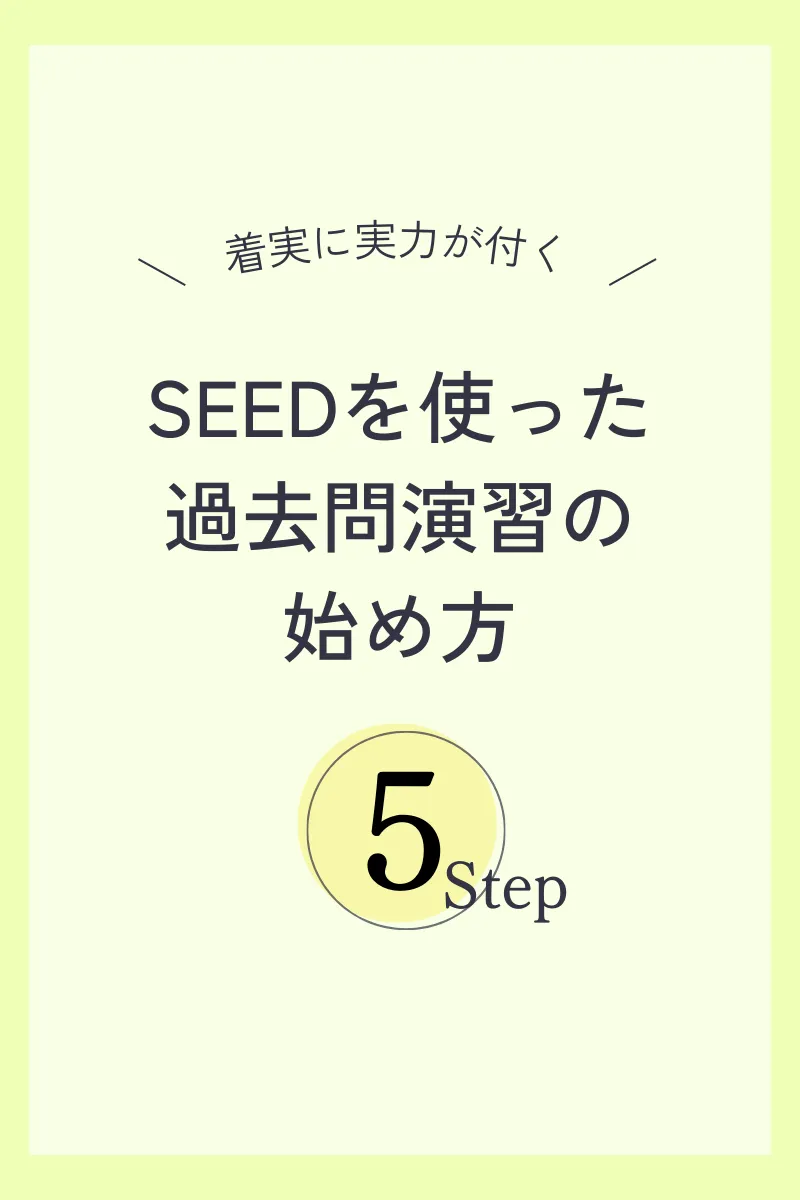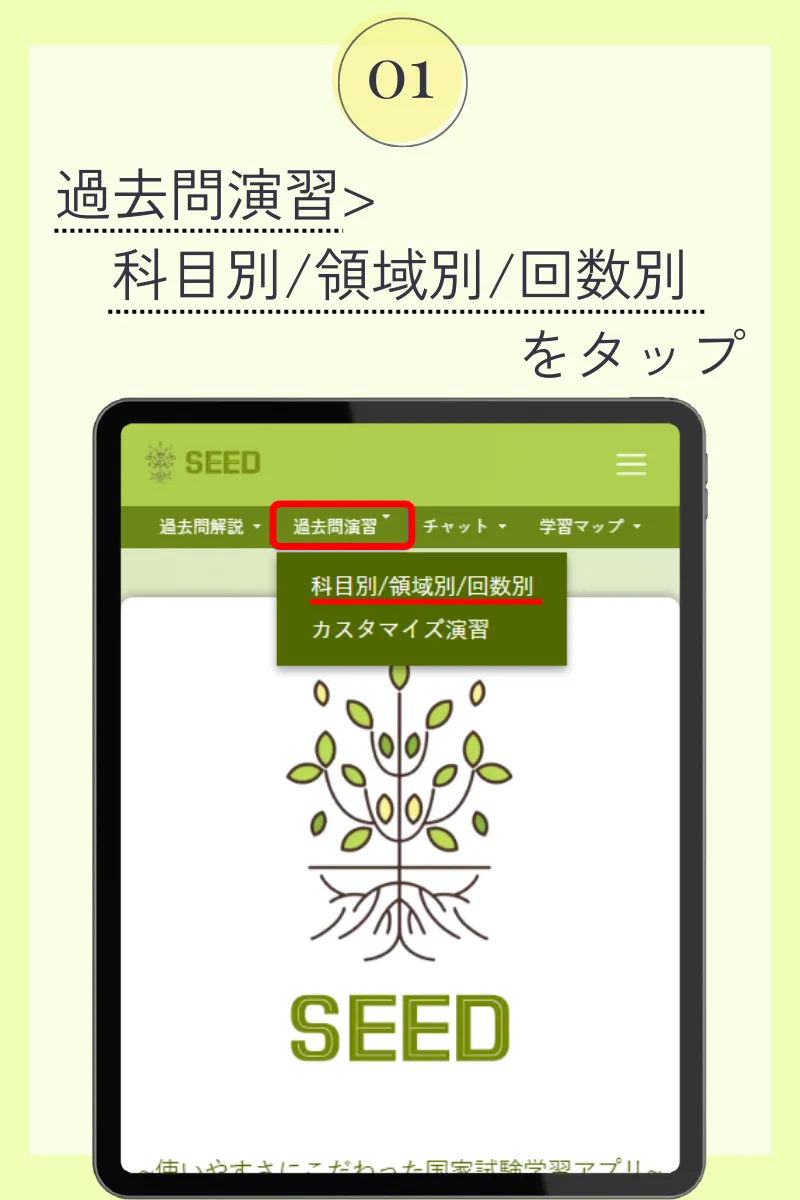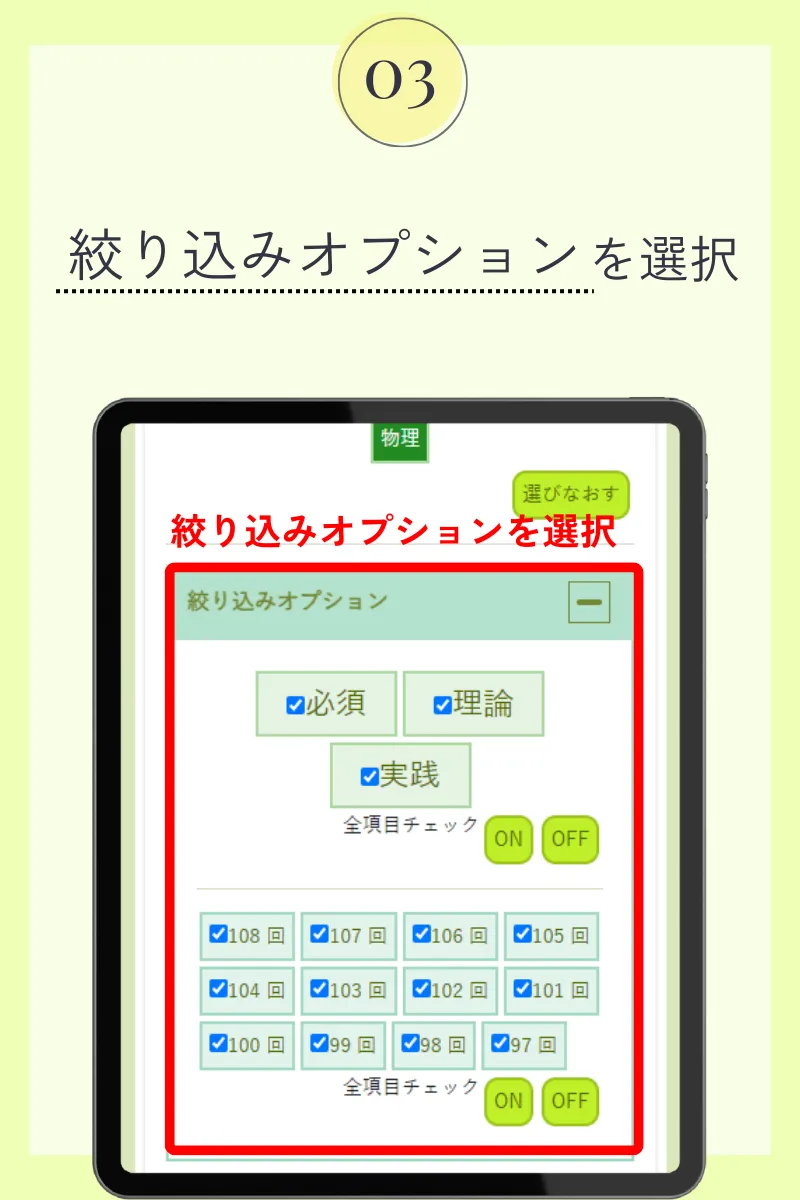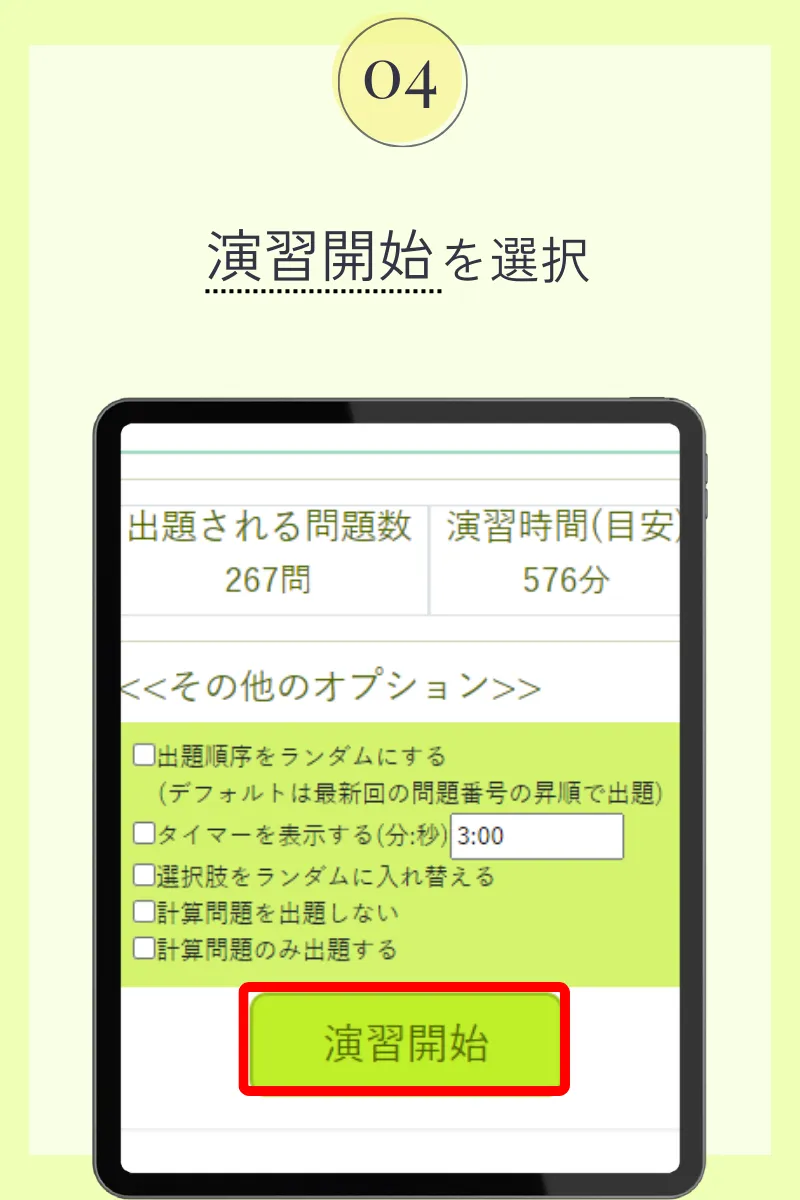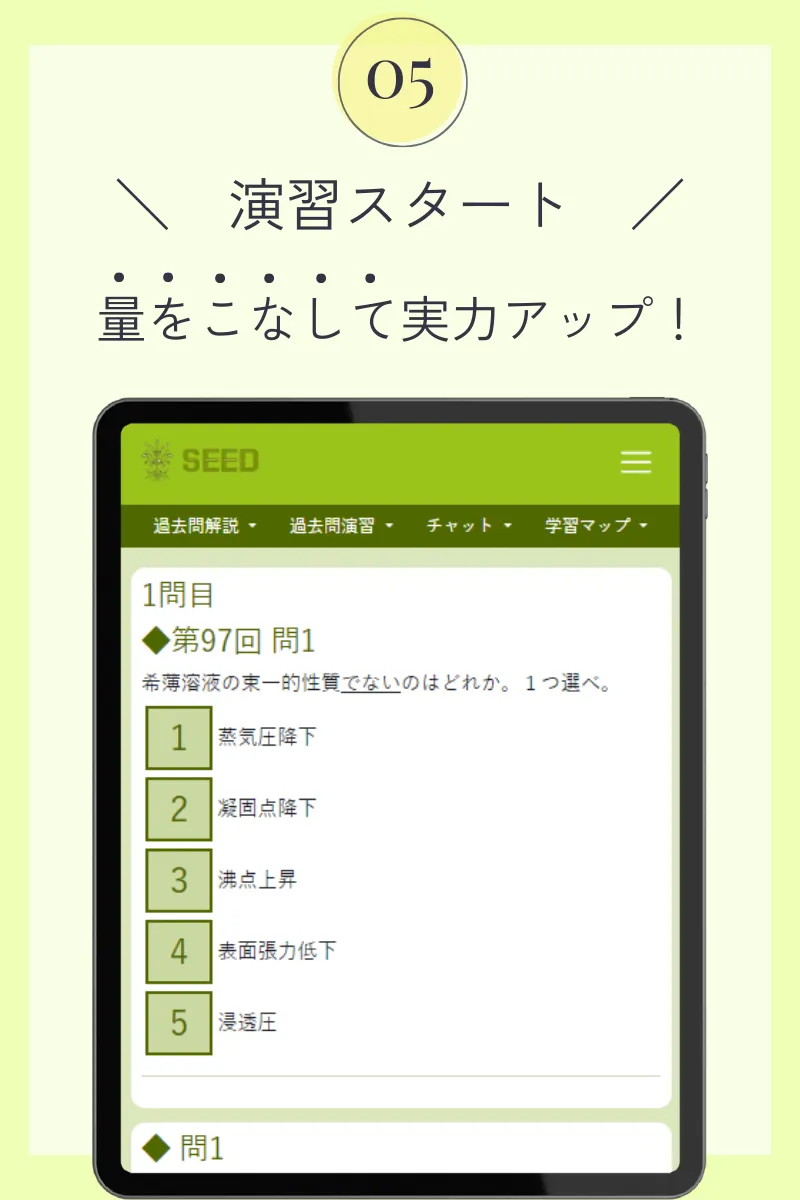第110回薬剤師国家試験
◆ 問161
過敏性腸症候群治療薬に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。-
ポリカルボフィルカルシウムは、胃内の酸性条件下でカルシウムを脱離し、腸管腔内において膨潤・ゲル化することで、水分バランスを調節する。
-
ラモセトロンは、求心性神経終末に存在するセロトニン5-HT3受容体を遮断することで、大腸痛覚の伝達を抑制する。
-
メペンゾラートは、副交感神経のセロトニン5-HT4受容体を刺激し、アセチルコリン遊離を促進することで、腸運動を亢進する。
-
トリメプチンは、消化管運動亢進時には、アドレナリン作動性神経のオピオイドμ受容体を刺激することで、腸運動を抑制する。
-
リナクロチドは、胆汁酸トランスポーターを阻害し、胆汁酸の再吸収を抑制することで、腸管内に水分及び電解質を分泌させる。
◆ 問161
◆領域・タグ
◆正解・解説
正解:1、2
※10~40秒程度掛かります。APIリクエストエラーが発生した場合は再実行することで解消される場合があります。
投稿しました!
◆ユーザー投稿の解説
ゲスト さんが投稿
``` **解説:** 過敏性腸症候群(IBS)治療薬に関する問題です。各選択肢の正誤と根拠は以下の通りです。 **1. ○ ポリカルボフィルカルシウムは、胃内の酸性条件下でカルシウムを脱離し、腸管腔内において膨潤・ゲル化することで、水分バランスを調節する。** * **解説:** ポリカルボフィルカルシウムは、高分子の親水性ポリマーであり、胃酸によってカルシウムが遊離し、腸管内で水分を吸収して膨潤・ゲル化します。これにより、腸管内の水分量を調整し、便秘型IBSでは便を軟化させ、下痢型IBSでは余分な水分を吸収する効果があります。 **2. ○ ラモセトロンは、求心性神経終末に存在するセロトニン5-HT3受容体を遮断することで、大腸痛覚の伝達を抑制する。** * **解説:** ラモセトロンは、セロトニン5-HT3受容体拮抗薬であり、特に男性の下痢型IBSに有効です。消化管の求心性神経終末にある5-HT3受容体を遮断することで、内臓知覚過敏を抑制し、腹痛や不快感を軽減します。 **3. × メペンゾラートは、副交感神経のセロトニン5-HT4受容体を刺激し、アセチルコリン遊離を促進することで、腸運動を亢進する。** * **解説:** メペンゾラートは、抗コリン薬であり、アセチルコリン受容体(ムスカリン受容体)を遮断することで、副交感神経の作用を抑制します。そのため、腸運動を抑制する効果があります。セロトニン5-HT4受容体を刺激するのは、モサプリドなどの消化管運動賦活薬です。 **4. × トリメプチンは、消化管運動亢進時には、アドレナリン作動性神経のオピオイドμ受容体を刺激することで、腸運動を抑制する。** * **解説:** トリメプチンは、消化管運動調節薬であり、消化管運動が亢進している場合は抑制し、低下している場合は促進する作用があります。しかし、その作用機序はアドレナリン作動性神経のオピオイドμ受容体を刺激することではありません。トリメプチンは、消化管の様々な受容体(セロトニン受容体、オピオイド受容体など)に作用し、消化管運動を調整すると考えられています。 **5. × リナクロチドは、胆汁酸トランスポーターを阻害し、胆汁酸の再吸収を抑制することで、腸管内に水分及び電解質を分泌させる。** * **解説:** リナクロチドは、グアニル酸シクラーゼC受容体作動薬であり、腸管上皮細胞のグアニル酸シクラーゼC受容体に結合し、細胞内cGMP濃度を上昇させます。これにより、CFTR(嚢胞性線維症膜貫通調節因子)を活性化し、腸管内への水分および電解質の分泌を促進し、便秘型IBSに効果を発揮します。胆汁酸トランスポーター阻害薬は、胆汁酸の再吸収を抑制することで同様に腸管内に水分を保持しますが、リナクロチドの作用機序とは異なります。 ```
Good: 0
Bad: 0